一番好きなフォントは?と聞かれたら、
「ん〜、やっぱりまだMB101かなぁ〜」と、
微妙なニュアンスで答える。MB101とは、モリサワの代表的ゴシックフォントで、Light・Reguler・Medium・DemiBold・Bold・Heavy・Ultraと7段階のウェイトを持っている。一番多用するのは、見出しやタイトル用としてのBoldとHeavy。
ちなみに書体見本帳の見本用センテンスといえば写研の「愛のあるユニークで豊かな書体」が定番だけど、本日の書体見本センテンスは、これ。
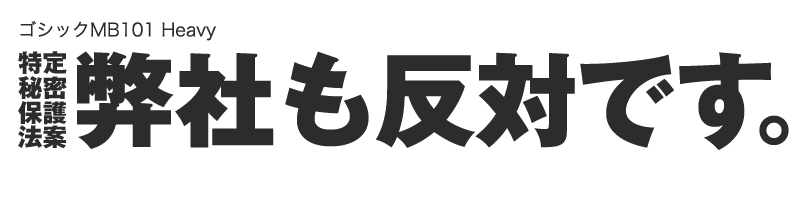
ん〜、やっぱりいい。
僕が好むフォントは、「言葉」を強く伝えるフォントだ。
人が何かを読み理解する場合、その人には、「言葉」より先に「文字」が届いているはずだよね。あたりまえだけど。それがお喋りなら、「言葉」より先に「声」が届くように。つまり書体を選ぶとは、どういう声でしゃべるかということ、とも言える。
そこで、読む人に、その「文字」「声」を可能な限り意識させずに、「言葉」そのものだけが強く伝わる。そういう機能として透明な書体が好ましい。
その意味では、同様にスタンダードな書体で、カタチとしてもスッキリしているヒラギノ角ゴも悪くない。見出しとしては弱いのだけど、ヒラギノ角ゴW3は、iPhoneの新しいOSにも使われてあの「フラットデザイン」 な世界観を決定づけつつフラットすぎない「言葉」感によって、品を与えている。
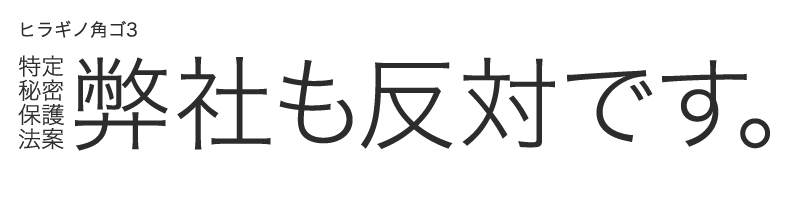
しかしそれらのモダンゴシック系の書体、なかでも下の「M+」なんかを見ると、やはり「言葉」の言葉たるナニカがスポイルされたちゃった感がある。カタチの単純化が逆に文字の存在を浮かせて、読むというより文字を目で追ってるという意識が薄ぅ〜くだけど、のぼってくる。人工的な音声への違和感のような。

ただ、「言葉たるナニカがスポイルされる」というのは、いかにもモダンな機能と言える。その意味では、抑揚を持つMB101は、逆に、やや「うざく」見えてきたのかもしれない。そのへんの感触が、冒頭の答え方のニュアンスでもあります。
ところで、ここでひとつ大切なこと。
「言葉」を伝える「文字」というのは、その言葉が持ってるイメージを「文字」のカタチで補完したり、「文字」のカタチを「言葉」のイメージにヨせることではない。
たとえば、この言葉を「楷書体」で印字する。
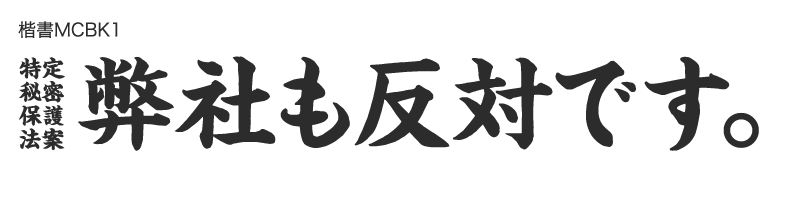
確かにある種のいかにもな雰囲気が出てきた。
さて、どうだろう、実際いろんなレベルはあるけれど、仕事で求められることの多くが、とどのつまり、こうした、いかにも感を演出する作業じゃないだろうか。これがグラフィックデザイナーの仕事でしょ。というムキもいるかもしれない。が、それはぜんぜん違う。
こうした作業は、コミュニケーションのスピードをあげるし、ひとつの技術ではあるけど、「言葉」を「文字」で拘束することであり、「言葉」を「文字」の中に閉じこめることに他ならない。
たとえば、「写真」と「言葉」というふたつの要素で構成されているグラフィックがあったとしたら、その言葉は、なるべく裸で置かれるべきで、だからこそ本当の意味で言葉と写真が響き、新しいイメージが生まれるんだと考える。
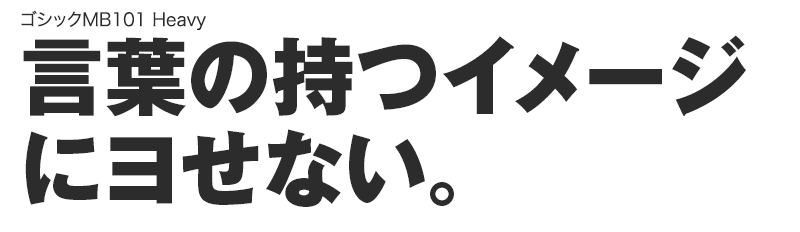
以上、大切なこと。でもこれは間違った考えかもしれない。
ということで、現在というか、ここ20年以上、さまざまな相対化に耐えている希有なフォント、それがMB101。というお話し。
と言いつつ、ここで書いたことは、僕のフォント選択におけるあくまで基本態度というか、通奏低音。
表面的な流れはもちろんあって、最近は、メイリオがキてるし、昨年は、あんなに敬遠していた手書き風フォントに、どハマり。某クライアントのロゴから名刺まですべてを「ふい字」で作成。それはそれで良いものが出来たんだけどね。
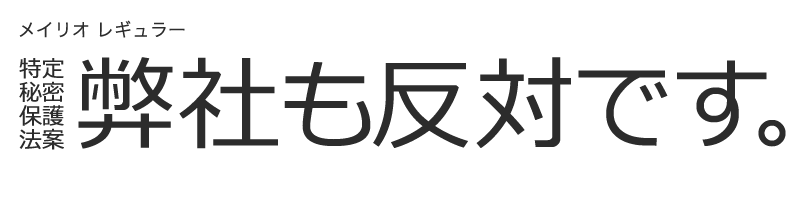
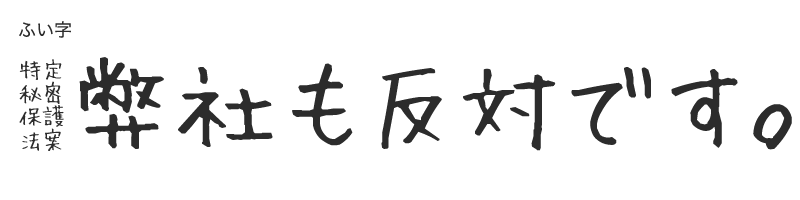
上のメイリオ レギュラー、「言葉」感は弱いんだけど、外に開いた明るさがきもちよく、フォント名の「メイリオ」は「明瞭(メイリョウ)」からつけられたというだけあって、小さなサイズでも読みやすい。ウインドウズPCでもきれいに表示される数少ないフォントのひとつでもあり、最近多用してる。
「ふい字」は数ある手描きフォントの中でも、もっとも使われたフォントじゃないかな。手描きフォントというとどこか媚び系なものがほとんどなのだけど「ふい字」はふっつーなところがウけたんだろうね。
フォントって面白いよね。